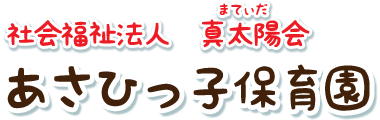お知らせ
給食について
☆子どもたちの食事で大切なのは、食べることを楽しむこと
「食育」ってどういうこと?生きる力を育むこと。
「嫌い」って思う前に、「これ何だろう?」って、興味をもつこと。
子どもが食に対して意欲的になると、それまで食べれなかったものが、食材を知ることで、触れることで、身近で育てることで、食べられるようになったりします。
そんな、体験ひとつひとつが、「おいしい」「楽しい」につながります。
「食育」って、難しくない、まずは楽しく食べることから始めましょう。
| 1.心と体を育てる楽しい食事 |
|---|
| 子どもたちの心と体を健やかに育む食生活。保育園においても、一人ひとりの発達段階や家庭状況に合わせて「食育」を実践し、乳幼児期から正しい食習慣を身につける必要があり、園内外の研修会や勉強会を進めながら、職員で試行錯誤し取り組んでいます。そのような中で子ども達の食に対する興味や関心、マナー、感謝の気持ちを育てる事を大切にしています。 保育方針でも、保育所における食育は、健康な生活の基本としての「食を営む力」の育成に向け、その基礎を培うことを目標として実践しなければならないということがうたわれています。保育目標でもそのことをふまえつつ、よりよい食育をすすめていくために、保育士一人ひとりが食に対する学びを深めるため、園内研修会を行い、学びを大切にしています。 |
| 2.子どもたちの食に対する楽しいこころみ |
| ①テーブルも決まった場所で、決まった友だちと限定するのではなく、色々な友だちと関わることによって、友だちを大切にする心、友だちへの興味を広げることへと導く。 ②子どもたちの当番活動は配膳をはじめ、その日の食材紹介を通して、様々な食べ物の名前や働きを知る。 ③行事食に取り組んでいます(こどもの日や七夕・ひなまつりなど)。 季節に合った行事を楽しくもりあげる、目で見て楽しく食べておいしい! |
☆保育園内の調理室で、調理業務を行います。
☆0歳児は、人工栄養および離乳食と、おやつを支給します。母乳の授乳についてはご相談ください。
☆食物アレルギーやアトピー性皮膚炎のために給食での除去が必要な方は、お申し出ください。医師の処方、あるいは指示書などにより、できる限りの対処をします。
保護者と保育園の連絡について
あさひっ子保育園では、お子様が毎日健康で、元気に過ごすためには、保護者と保育園が十分にコミュニケーションをとり、協力し合うことが大切であると考えます。 保育園での状況やご家庭の状況を相互連絡しあうために、おたより帳があります。体調、遊び、覚えたこと、挑戦している事、失敗したことなど、どんなことでもご記入してお子様の育ちの様子をお知らせください。 また、保護者の疑問、どうして?などもおたより帳、又は直接お尋ねください。私達は常に誠意をもって保護者と共にお子様の健やかな成長を支えます。おたより帳を上手に使ってお子様の成長の記録を残しましょう。 「おたより帳は保育園と保護者(家)を結ぶ、信頼という絆の架け橋です」
衛生管理等について
1.集団給食施設届出を宮古保健所へ届出済です。
2.給食現状報告の届け出を毎年、保健所へ届け済みです。
3.禁煙施設、認定証を保健所より受けております。
4.軟水器を設置し毎朝水質検査を行っています。
5.食器・調理器具の殺菌、洗浄を行っています。
緊急時の対応について
1.保育中に容態変化などがあった場合、あらかじめ保護者が指定した緊急連絡先へ連絡をし、委託医又は、必要な医療機関に連絡を取り必要な措置を講じます。
2.保護者と連絡が取れない場合は、こどもの安全を最優先させ、当園が責任を持って、しかるべき対応を行いますので、あらかじめご了承ください。
| ◎非常時の対応 |
|---|
| 火災、地震、防犯等非常時の対策は月1回訓練等で周知徹底しています。 |
| ◎保育園に対する意見・苦情について |
| 保育(保育園)に対する疑問、苦言、提言、相談、どんな小さなことでもお申し出ください。電話、おたより帳、お手紙、直接、どんな方法でも構いません。 誠意をもって問題解決に当たります。 |
保健と健康管理について
昨夜熱があったとか、ご家庭でけがをしたなど健康上に変わったことがあれば、登園時に必ずお知らせください。
| ★ | 朝、体温が37.5℃以上の時や、下痢や嘔吐が頻繁にあるなど体調不良の時は、登園せず家庭保育をお願いします。また、受診をおすすめします。 |
|---|---|
| ★ | 病欠連絡の時は、必ず病名や症状をお知らせください。 |
| ★ | 保育中の園児に異常(目安として発熱37.6℃以上のときや、ケガなど)があった場合は、保護者に電話します。常に連絡が取れるようにしておいてください。 子どもたちの安全を最優先させ、速やかなお迎えをお願いする場合や、保護者の了解を得ずに受診させる場合があります。 |
| ★ | 集団生活ですので、各種予防接種は必ず受けてください。未接種の場合、保育をお断りすることがあります。 |