日時 4月8日(土) 午前9時〜
場所 原町聖愛保育園ホール
出席者 全園児・全保護者
お祝い会終了後、クラスでの話し合いと、記念撮影(クラス毎)を行います。
(でんし・つぼみ親子、はな組以上園児のみ)
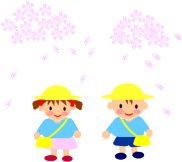
三月は保育者にとっても締め括りの月です。自分の保育を振り返ってみると、あれをしてこなかった、ここがまだ出来ていないと、やり残したことが頭をよぎり、責任の念の一抹の不安や焦りのような感覚も覚えます。しかし、子ども達一人ひとりの一年を思い返した時には、成長がはっきりと感じられ、喜びに満たされます。
随分前のことです。あるお母さんが、一歳の我が子の後ろ姿に「大きくならないで」と、一言言ったのを聞いたことがありました。今が可愛いのでこのままで居てということなのか、親のオモイよりも成長が早く、何か不安を感じて出た言葉だったのか、真意は分かりません。が、その言葉の奥に、大人の身勝手さと子離れの歪みを、垣間見たような気がします。
神様に造られた生命は必ず成長します。精神科医によると、<成長しないでと期待された子どもは、年齢の割りに精神年齢や行動が幼く、いつまでも親の庇護のもとにとどまりがちである>、と言われています。
一・二歳児クラスで、「大きくなったね」と一人の子どもに声をかけると、喜ぶ本人はもとより、言葉を聞き逃さなかった子どもまでもが、僕も私もと胸を張って見せ、「大っきいでしょ、ほら」と自己アピールをします。表情は誇らしげで、未来への賜物を秘めていることを感じさせます。
認めてもらう喜びは、おもちゃなどでは得ることが出来ない、子ども自身が自分を成長させるのに大事な、心の栄養になるのです。
『育てたように子は育つ』。こんなタイトルの本がありました・・・。
お子さんの成長を、家族みんなで心から喜び合いましょう。
| ≪3月の行事予定≫ | |||
| 日付 | 園の予定 | 職員の予定 | |
| 1日 | (水) | 子育てサークル) | 職員会議 |
| 2日 | (木) | ポップコーン | 避難訓練 |
| 3日 | (金) | ひなまつりお楽しみ会 | |
| 4日 | (土) | 入園説明会 | |
| 7日 | (火) | 合同礼拝 | 職員聖書研究会 |
| 8日 | (水) | 子育てサークル | マネージャー会議 |
| 9日 | (木) | いちご狩り(世代間・ほし) | 園内研修 |
| 13日 | (月) | しゃりん梅訪問 | ちいろば会理事会 |
| 14日 | (火) | 職員聖書研究会 | |
| 15日 | (水) | 子育てサークル | ケース会議 |
| 16日 | (木) | ポップコーン | 園内研修 |
| 18日 | (土) | 卒園児交流 学校の話を聞く・小1 | |
| 20日 | (月) | 小人さんの音楽会 | |
| 21日 | (火) | 春分の日 休園 | |
| 22日 | (水) | 給食会議 | |
| 24日 | (金) | お別れ遠足 愛情弁当 | |
| 27日 | (月) | 小人さんの音楽会 | |
| 28日 | (火) | お別れ会 | |
| 29日 | (水) | 2005年度 第57回 卒園式 | |
| 31日 | (金) | 保育終了 | |
| 2006年度 入園・進級をお祝いする会 日時 4月8日(土) 午前9時〜 場所 原町聖愛保育園ホール 出席者 全園児・全保護者 お祝い会終了後、クラスでの話し合いと、記念撮影(クラス毎)を行います。 (でんし・つぼみ親子、はな組以上園児のみ) |
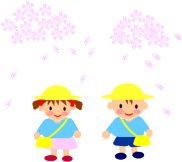 |
| 2005年度 第57回 卒園式 日時 2006年3月29日(水) 午前9時30分〜 場所 原町教会 礼拝堂 出席者 つき、ほし組園児・つき組保護者・職員 成長の喜びを皆でお祝いします。 在園児を代表して、ほし組の子どもたちが式に参列します。 (詳細は後日お知らせします) 楽しかった思い出を胸に・・・ 神様に守られて日々を楽しく過ごした子どもたちは、心身共にたくましく成長しました。神様に感謝しながら、残された日々を大切に過ごします。今まで仲良く遊んだつき組やお別れする友達との交流も予定しています。 |
 |
| お別れ遠足 3月24日(金) つき・ほし 丸森町 不動尊キャンプ場 なみ・はな 東ヶ丘公園 つぼみ・てんし 堤付近 *詳細についてはクラス便りをご覧下さい。 |
| お別れ会 3月28日(火) 全園児 保育園ホール 子どもたちに伝えたいもの 今年度は、『森と川』をテーマに保育を進めてきました。 自然に親しみ、保育や遊びに取り入れて様々な恵みを感じてきました。 同じ場所を歩いて、まわりの物を見たり触れたりすることは、一年を通すことで更に変化に気づくことが、子どもたちの反応からはっきりとわかりました。 小さな石ころにも模様の美しさや感触の違いなどがあることに気づき、それらを宝物にする子どもたち感性を豊かに育む環境を私たちは大切にしたいと考えています。 |
| 来年度の保育テーマは『川』です。 新たな発見や感動を沢山引き出せるような保育を展開していきます。 今後も、私たちの身の回りにある自然を守り、活用して、幼児期に何を大切にしていかなければならないか?を、考えられる心が育つ保育をめざしていきます。 |