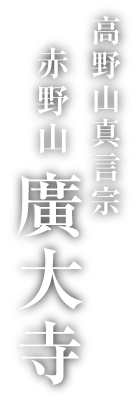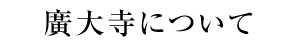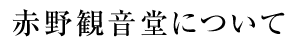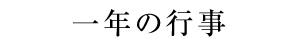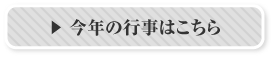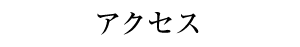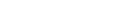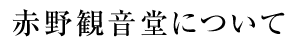
江戸時代より駿河一国三十番札所及び横道(よこどう)十五番札所として知られています。
この赤野観音堂は、市内では数少ない江戸前期頃の建築様式を示す建物で、市指定有形文化財となっています。木造、茅葺き、寄棟造の平屋建てで、外陣は唐様式の鏡天井で、天井には龍、正面両側の壁面には飛天(天女)の舞う姿が描かれ、鏡天井の周囲は化粧屋根裏になっています。屋根の茅葺きを除き創建時そのままなのでかなり老朽化し、極彩色の絵画も薄れていますが、よくまとまったお堂で、「ぬまづの宝100選」に選ばれています。
この辺りの地名を阿気野といい、もとは阿気大神が祀られていたと伝えられています。この神社は現存しませんが、その本地と考えられる寺院の観音堂だけが残り、現在は廣大寺が管理しています。
また、この建物には左甚五郎が藁人形に手伝わせて造ったという、わら人形伝説が伝えられています。
本尊は、十一面観音像(市指定有形文化財)で、頭部から胴心部及び両臂(りょうひ)まで共木から彫りだされた純粋な一木造の像となっています。現在は木肌を現し、天衣にわずかに赤色の顔料が残り、全体的に素朴な作風になっています。 なかでも両耳の内耳を省略し、両肩のあたりに丸ノミのあとを残している作風は、東国に流行した鉈彫(なたぼり)に近いものがあり、本像が小高い丘の上に祭られていることとあわせ、11世紀頃この地で製作された仏像であることを物語っています。
境内にはカヤの大木(市指定天然記念物)があり、目通りは3.9メートルで樹勢もさかんです。
なお、この近くの川原には八畳石と呼ばれる大きな石があり、石の上で白隠禅師が修行したという言い伝えや、この石から抜け出て洪水を起こしたというほら貝の伝説も伝えられています。