
年末年始の静かだった園舎に、子どもたちの弾んだ声と笑顔が戻ってきました。私たち職員も子どもたちと一緒に心弾ませる一年を過せるよう、はつらつとした笑顔で子どもたちを迎え入れたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
 |
新年明けまして、おめでとうございます。 年末年始の静かだった園舎に、子どもたちの弾んだ声と笑顔が戻ってきました。私たち職員も子どもたちと一緒に心弾ませる一年を過せるよう、はつらつとした笑顔で子どもたちを迎え入れたいと思います。 本年もどうぞよろしくお願いいたします。 |
誕生したばかりの赤ちゃんは不思議です。見えない目でオッパイを探し当て、お乳を飲もうとするあの生命力はどこから来るのでしょうか。それは動物たちにも同様の自然の生命力です。神様が与えてくれた本能に違いありません。
「自らの力で生きよ!」。これはすべての生命に与えられた神様からの恵みです。親の責任は、子供が生まれながらに備えている自然の生命力に従ってその子らしく育てていくことで、親の希望に合わせてそのたくましさを奪うことではありません。
夫婦は互いに「よき助け手である」という聖書の言葉はまた親子にもあてはまることで、親は支配者ではなく、どこまでも子供にとって「よき助け手」として、その人格形成の責任を担っています。子供の性格と能力をきちっとみきわめながら、その子に最もふさわしい成長の場を与えていくことが大切です。でも何をどうしたら良いのか、難しいです。いろいろな子育て論、教育論があって困ります。先日も、どうしてよいかわからなくなって、我が子を殺してしまった母親がいました。子供だけじゃなくて親にとっても現代は受難の時です。でも見捨てないで下さい、子供に希望を与えてください。
「今日、親のなすべきことは何だろう」ということがよく話し合われます。ここにも何なに論が出て来ます。しかし論は子を殺す。あえて言うならば、「今日、親は何をなすべきでないか」ということのほうがはるかに重要なことです。子供が自然の生命力に従っていきるために親はなるべく手をかけない。極端なことを言うと「どれだけ自由にさせる」ことができるか。親が子供に手をかけ過ぎ、何から何まで形を作ってやり管理していくということよりも、枠をはめないで育てていくことの方が、知恵と勇気を必要とします。育児放棄やほったらかしを勧めているのではありません。育児は保育園、後は「ほったらかし」はいけません。勿論、しっかり見ながらどこで親の手をかけるかが、子育てのこつです。共に健やかに生きてください。
![]()
| ≪1月の行事予定≫ | |||
| 日付 | 園の予定 | 職員の予定 | |
| 4日 | (土) | 保育開始(午前保育) | |
| 7日 | (火) | 合同礼拝(つき・ほし組) | |
| 8日 | (水) | しゃりん梅訪問(ほし組) 子育てサークル | 職員会議 |
| 9日 | (木) | 年少・年長話し合い | |
| 14日 | (火) | 聖書研究(めぐみの会) | |
| 15日 | (水) | 白鳥見学(つき・ほし組・子育てサークル) | マネージャー会議 |
| 20日 | (月) | 避難訓練(図上訓練) | |
| 21日 | (火) | 合同礼拝(つき・ほし組) | 聖書研究(タラントの会) |
| 22日 | (水) | 子育てサークル | 企画会議 |
| 23日 | (木) | 年長話し合い | |
| 27日 | (月) | 愛情弁当の日 | |
| 28日 | (火) | しゃりん梅訪問(ほし組) | |
| 29日 | (水) | 子育てサークル | 給食会議 |
|
【白鳥見学 1/15(水)】 |
|
◆ 行き先 楢葉町「白鳥の館」 ◆ 対象 つき・ほし組・子育てサークル 自然に生息する生命ある生き物は、大きくても小さくても私たち人間と同じく、地球上に生きているものです。生き物と触れ合うことが少なくなった昨今ですが、今回は渡り鳥である「白鳥」を見学してその特性を知ったり、生き物の素晴らしさを肌で感じてほしいと願っています。 ・ 必ず防寒着着用で、8時30分まで登園。 ・ 白鳥の餌(パンくずや米など)の、持ち寄りのご協力をお願いします。 |
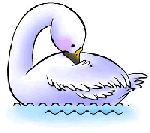
|
|
【世代間交流事業「伝承遊び・お宅訪問」】 |
|
| つき組さんが昔なつかしいお正月の遊びを、一人暮らしのお年寄り宅へ訪問して、教えていただきながら楽しい一時を過してきます。 その時には、ささやかではありますが、おじいさん、おばあさんへ手作りの贈り物をしてくる予定です。 |
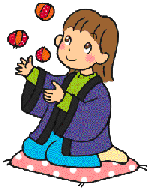
|
|
【予告・ご案内】 |
|
* 今年度最後の「保育参観」を予定しています。
詳細については後日改めてご案内いたします。 |

|
|
【子どものからだを育てる環境づくり】 |
|
| 月刊本「キリスト教保育」村上哲朗(和洋英和女学院大学教授)の記事より ひと昔前は、四季を感じる自然と一緒に遊び回ったり、異年齢児の友達との小さな社会交流があったのに、最近はテレビやビデオ、そして何よりテレビゲーム、ファミコンなどが、大きな遊び道具となっています。その結果、外遊びの足りなさや人との触れ合いの少なさが、脳(前頭葉)の発育不良に影響を及ぼしているようです。 また、食習慣の悪さ、寝不足、運動不足、外遊びをしたがらないなどの生活の乱れが見られ、そのためもあってアレルギーをもっていたり、すぐに疲れたと言う子や皮膚がカサカサ、背中が曲がっていたり、咀しゃく力が弱い、喘息の症状があらわれたり、イスにじっと座っていられない、転んでも手を出せない、頭痛や腹痛などを訴える子が多く見られるようになりました。 遊びや生活体験の不足は脳の運動不足とも言えます。子どもたちの体には、ダイナミックな粗大運動が不可欠です。その大きな筋群の運動があってこそ、初めて手を使った小筋群の動きが巧みになっていくのです。 いろいろなバランスを高める遊びから器用さが養われます。創造力から好奇心が生まれ、好奇心の継続が集中力を高めていくのです。 昔は、特別な運動をしなくても生活そのものが、成長と発達に関わる動きでしたが、現代社会の便利さはワンタッチで作業を終えることなど、動かなくても出来ることが増えました。 と記事はまだ続きます。 保育園で過す6歳までの生活経験は、身体の成長、心の成長、いずれにおいてもこれからの基礎になるものですが、同じに子どもが育つ環境の大切な一つに、生活リズムがあります。 生活リズムは睡眠や食事、遊び、感心や意欲など生活全般に関係し、子どもの成長に大きな影響を与える大事なものです。 保育園ではご家庭と一緒にこれらのことを考え、望ましい生活リズムの確立と、その時期に必要な様々な経験が出来る環境の整備を行い、保育を勧めていきたいと考えています。 |
 |