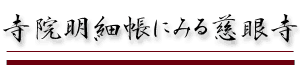 |
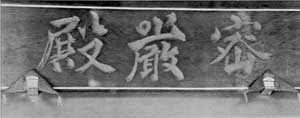
密厳額(先代定全師筆) 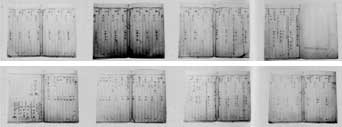 「本末一派寺院明細帳」都立公文書館所蔵 |
| 明治8年から12年 (1875〜9)にかけて各寺院から明細帳が提出されました。これを「本末一派寺院明細帳」と称しています。 当慈眼寺の「本末一派寺院明細帳」は、明治10年に提出されていますが、蓮光院住職・観盈(かんえい)和尚によって記されています。 明治元年(1868)、廃仏毀釈・神仏分離令の発布いらい、還俗する僧が多く、いわゆる無住の寺が多出し、明治新政府が周章狼狽したという事実が残されていますが、慈眼寺も明治初年頃から、10年ごろにかけて、無住であったことが、この文書によって明白です。 観盈和尚によって記載された「明細」は、実に克明をきわめており、真摯な調査がなされたに違いありません。 境内地476坪、境外地は実に二町四段四畝二十六歩、約7300坪もあったと記載され、当寺がいかに庶民の信仰をあつめていたかを、如実にものがたっています。 |
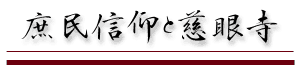 慈眼寺の現在地は多摩川を眼下に望む、
瀬田の崖の上にあります。 開創当時はこの崖下にあった修験道場でした。 古老の話では、大正から昭和初期にかけて、 修験所の名残りの跡と思われる滝があり、
夏になるとこの滝へ涼を求めて、 近在の人びとが通ったということです。 地理的には、厚木(神奈川県)から多摩川を二子の渡しで渡る大山街道に面し、
西南に甲斐、相模の山陵の眺望がよく、文人墨客の杖をひくものが少なくなかったと伝えられています。 近隣の村人たちや、この大山道を往き来した人たちが、
静寂な地に法燈をともす慈眼寺へ参詣に訪れてきたのでしょう。 慈眼寺の現在地は多摩川を眼下に望む、
瀬田の崖の上にあります。 開創当時はこの崖下にあった修験道場でした。 古老の話では、大正から昭和初期にかけて、 修験所の名残りの跡と思われる滝があり、
夏になるとこの滝へ涼を求めて、 近在の人びとが通ったということです。 地理的には、厚木(神奈川県)から多摩川を二子の渡しで渡る大山街道に面し、
西南に甲斐、相模の山陵の眺望がよく、文人墨客の杖をひくものが少なくなかったと伝えられています。 近隣の村人たちや、この大山道を往き来した人たちが、
静寂な地に法燈をともす慈眼寺へ参詣に訪れてきたのでしょう。 |
 参道入口の庚申塔 |
|
||||
| 慈眼寺の庚申塔は、参堂入口の脇にひっそりとたたずんでいます。 路傍の石仏の中でも、最も親しまれ、当寺の庚申塔は「見ざる」「聞かざる」「言わざる」 という謹慎態度を示す三猿の上に、三ツ目・腕六本の青面金剛が刻まれている典型的な江戸中期のもので、造立年月日が「元禄十丁丑年二月廿日」と判読されます。 | |||||
|
|||||
| 昭和期に入り、川崎大師平間寺を一番寺として、 弘法大師有縁の古刹を巡る八十八ヶ所に構成されたものです。 もちろん、四国八十八ヶ所霊場巡拝を写したもので、 慈眼寺は第三十七番霊場札所になります。 第八十八番霊場の宝幢院(東京都大田区西六郷)まで、 神奈川の横浜市から川崎市、東京の世田谷区、大田区、品川区を辿る巡拝路ですが、 一番二番の順は気にせず、機会あるごとに参詣しつづけていきたいものです。 | |||||
 不動明王像 |
|
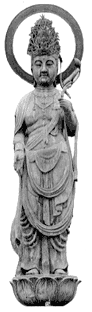 興亜観世音菩薩 |
|
|
|||
| 「観音菩薩」は、正しくは観世音菩薩(かんぜおんぼさつ)あるいは観自在菩薩(かんじざいぼさつ)といいます。
慈眼寺の観音像は、興亜(こうあ)観世音菩薩と称します。 宝冠をいただき円光をつけ、身に条帛・裳(正しくは裙)をまとい、
天衣をかけて、蓮華座の上に、ややうつむきかげんにお立ちになっています。 昭和15年に造立され、現在は本堂正面の右手にありますが、旧本堂の頃は、本堂正面にありました。 世田谷三十三観音は、文字通り区内の由緒ある観音像を巡拝するもので、 静寂な住宅街と化した区内を、おりをみては現世利益を願って巡拝してみたいものです。 |
|||