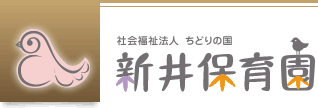「SIあそび」とは、米国カリフォルニア大学のJ・P・ギルフォード博士の知能 構造(SI)理論に基づく、問題解決力と創造的思考力を育むための教育プログラムです。 「SI教育」または「知能教育」とも言います。
「知能教育」と「知識教育」の違いは、子ども自発性を土台にしているか?いないか?です。 無理やり納得させたり、覚えさせたりすることは逆に、知能の働きを停止させてしまいます。 好きなことに熱中することが脳への刺激になり、集中力をつけるのです。
子ども達が将来、自分の才能を最大限に活かし、心豊かな人生を送れるようにするには、 著しく頭脳が発達する幼児期に、多面的な頭脳の使い方を沢山経験させることが非常に大切 になってきます。
☆ 学ぶ力 ・・・ 教えるのではなく「育てる」「育つ」
☆ 学ぶ姿 ・・・ 「結果」ではなく「過程」
-
1.考える力、やる気を起こさせる
「なぜ?」「どうして?」を保育士と一緒に導入教材より自分の考え、皆の前で はっきりと発表でき、自ら進んでやってみようという意欲を養います。 -
2.創造性、集中力を高まる
色々なカードやシートを使い、遊びの感覚で取り組んでいるうちに、理解力が高まり 「できた」「できない」ではなく、どこまでも自分で考えようとする集中力を養います。 -
3.自主性が育ち、自ら考えを築ける
様々なパターンの遊びのテーマ(知能因子)について、お友達の発表する色々な考え方 を理解し、更にそれらにとらわれることなく自分自身の考えを大切にし教材に取り組みます。 -
4.人前で発表することができ、意見交換ができる
自分の考え方を発表し、友達とどの様に展開したら良いか、納得がいくまで意見交換を 行うことにより、自分に自信が持てるようになります。


子どもが楽しめる教具で考える力を養う
新井保育園では、2才児クラスより創造性教育の先駆者であるJ・P・ギルフォード博士の知能構造(SI)理論に基づき、「できた」「できない」ではなく、自分で気づいていく過程を大切にしています。
人間の大脳は3才までに全体の3分の2が成長し、3才までに得た情報の量はその後の生涯の得る情報量に匹敵すると言われています。
この大切な時期に、吸収し発達する力をしっかりと受け止め、確かな成長を育むため、2才児が興味を持ち楽しめる専用の教具(積み木、シート)を用い、「2才児クラス・SIあそび」を取り入れ、毎日の保育の中で必要な「落ち着き」をSIあそびから学んでおります。